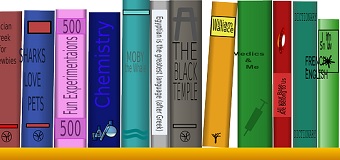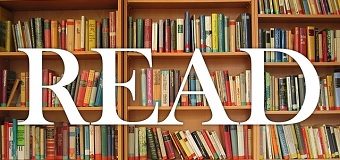Sponsored Link IPO前のタイミングだけではなく、丁寧なインタビューに基づいた読み応えがある一冊です。「韓流」という視点もぶれていません。IPO後も、親会社ががっちり株式を保有するからくりにもページを割いて …
カテゴリーアーカイブ: 書評Bookreview
滝田洋一(2016)『世界経済大乱』日本経済新聞出版社
G20(The Group of Twenty)の時代を痛感させられる1冊だった。G20は1999年、財務大臣・中央銀行総裁会議として始まり、2008年以降、首脳会議も開かれている。前者はアジア通貨危機、後者は世界金融危 …
清水功哉(2016)『緊急解説 マイナス金利』日本経済新聞出版社
EUの中央銀行(ECB)やスイス、デンマーク、スウェーデンに次いで、日本銀行もマイナス金利を採用した。民間銀行が日本銀行内の当座預金にある超過準備に対して、0.1%のマイナス金利を課すものである。 同書は、円高誘導の隠さ …
石川真由美編(2016)『世界大学ランキングと知の序列化 大学評価と国際競争を問う』京都大学出版会
大学教職員のほか、スーパーグローバルハイスクールの高校教員、そして、海外大学を目指す高校生は、ぜひ読んでみて欲しい。海外の大学ランキングの「ゲームのルール」に迫った一冊。